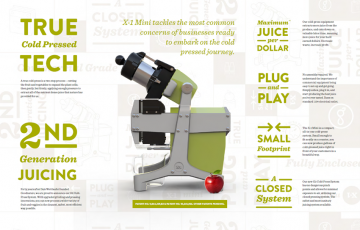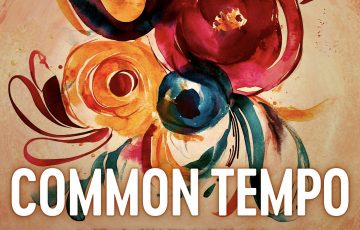- 機能性発酵飲料「_SHIP KOMBUCHA」の製造販売
- 100% Plant-Based/Naturalな素材にこだわったカフェ「1110 CAFE/BAKERY(川口市領家)、「BROOKS GREENLIT CAFE(港区南青山)」の運営
- 約3000坪の自社敷地を活用した各種イベントを開催
- 自社農場で野菜の有機栽培に挑戦
- サーキュラーエコノミーの実践 などなど
素敵な環境を創造し続け、世の中を笑顔で満たす活動をしている、大泉工場のKANです。
情報があふれすぎるこの時代、
「人から直接話を聞く」という行為は、むしろ価値が上がっているように感じる。
ほしい情報のほとんどは検索すれば出てくる。
SNSをひらけば勝手に誰かの意見が流れ込み、AIに聞けば要点を整理してくれる。
“情報を手に入れる”という行為は、今や驚くほど簡単だ。
それでも僕たちは、わざわざ時間をかけて人に会い、話を聞き、生で見に行く。
ときには高い旅費を払ってまで、視察という名目を掲げて。
「遊びに行ってるだけ」と言われることもあるけれど、
受け取り方や、誰と行くかによって、その行動はまったくの別物になる。
その不思議さを、今回改めて体感した。
先日、2泊3日の台北視察に参加し、“人の話をどう受け取るか”というテーマに辿り着いた。
今回の旅は、川口市の時代を築き上げてきた重鎮たちと、未来の川口をどう導くか──
そんなテーマで行動を共にする、なかなかに珍しい機会だった。
主題は「映像産業」。
大泉工場が今すぐ映像産業に参入するか、と言われると、その可能性は正直低い。
ただ、2009年からOKS CAMPUSを撮影場所として提供してきた歴史はある。
まったく関係がないわけでもない。
そんな背景から、旅のメンバーに加えていただいた。
台北松山空港は羽田から4時間もかからない距離だ。
ニュースでは「台湾有事」など、不安を煽る言葉が飛び交うが、
現地の空気は驚くほど平和で、街にはいつも通りの時間が流れていた。
政治的リスクはメディアがつくる物語であるかの如く、人々の暮らしは案外静かなものだ。
台北での3日間はほぼ分単位のスケジュール。
スタジオ見学、VR体験、日本コンテンツの配給会社とのミーティング……。
観光気分で行けば、開始1時間で心が折れるレベルの視察だった。
ただ、この“ハードさ”のおかげで、逆に気づけたことがある。
視察の価値の大半は、「誰と行くか」で決まる。
同じ場所を1人で見に行っても、得られる情報量はまったく違う。
テーマパークのように均一な体験を提供する世界ではなく、ここはビジネスの世界だ。
決裁権を持つ重鎮と同行していると、相手の“こちらにかける熱量”が明らかに変わる。
扱われ方が変わる、と言うと語弊があるけれど、ビジネスとして当然のことだ。
今回の視察でもそれを強く感じた。
最新スタジオの裏側も、設備投資の思想も、スタッフ育成の工夫も──
こちらが真剣に興味を示すと、驚くほど具体的に話してくれた。
その瞬間、僕ははっきりと理解した。
人の話は、相手との関係性で深度が変わる。
そしてその深度を決めるのは、“受け取る姿勢”である。
僕自身、映像事業にすぐ飛び込む予定はない。
でも映像コンテンツは好きだし、最新技術の話も面白い。
だからこそ、分からないところは素直に質問した。
「この技術は何が革新的なんですか?」
「どうやって人材を育てているんですか?」
「ここだけの課題って、何がありますか?」
すると、相手の表情がふっと変わる。
人は、自分の専門性への“正しい好奇心”に弱い。
真剣に聞かれると、もっと話したくなる。
喜んで内側を見せてくれる。
この“好奇心の循環”こそが、視察の本当の価値だと思う。
視察とは、ただの情報収集ではない。
人の心の奥にある“やってきたことの物語”に触れる行為だ。
その物語に触れた瞬間、頭ではなく“体で理解する情報”が生まれる。
そして、その物語に触れさせてもらえるかどうかは、こちらの姿勢次第だ。
・ただ話を聞くだけの人
・興味があるふりをする人
・深く知りたいと思っている人
視察先の案内人は、見れば分かる。
質問の質、相槌の深さ、表情の温度、メモの速度……。
そういう“小さなサイン”を相手は敏感に受け取っている。
今回、重鎮たちと過ごす時間の中で、僕は“受け取り方”の大切さを何度も感じた。
視察で最も重要なのは、「知識を持ち帰ること」ではなく、
相手の“温度”を持ち帰ることだ。
その温度が、自分の中で発酵し、次の行動や思考へと変わっていく。
事業領域が違うからといって、学びがないわけではない。
むしろ違うからこそ、自分の視野が広がる。
今回の旅も、映像事業参入を判断するためのものではなく、
“好奇心の筋肉”を鍛える旅だったのだ。
だからこそ、僕はこれからもどんどん首を突っ込むつもりだ。
専門家が当たり前に語る領域の外側から、
「それ、どういう意味ですか?」
「それって、なぜ必要なんですか?」
と、失礼にならないように踏み込んでいきたい。
首を突っ込むことは、時に勇気がいる。
でも、それができれば世界の見え方は変わる。
そして何より、人との信頼が生まれる。
“この人は本気で聞いてくれている”という感覚は、
どんな業界でも同じ価値を持つ。
最後に今回の旅で感じたことをもう一度まとめる。
視察の本質とは、“人の話をどう受け取るか”である。
情報はAIがくれる。
けれど、熱量は人に会わなければ受け取れない。
僕はこれからも、
他人の関心領域の内側に、好奇心という名の首を突っ込み続ける。
その先にある、まだ見ぬ可能性を取りこぼさないために。
そんな視察に行くチャンスも少なからずある大泉工場は、常に仲間を募集している。興味を持っていただけたら、ぜひ、エントリーしてください。