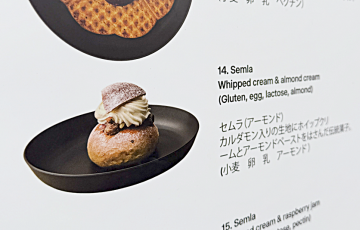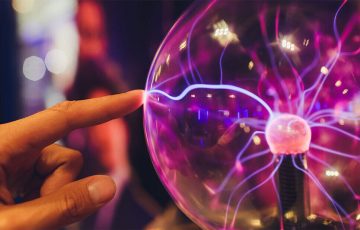- 機能性発酵飲料「_SHIP KOMBUCHA」の製造販売
- 100% Plant-Based/Naturalな素材にこだわったカフェ「1110 CAFE/BAKERY(川口市領家)、「BROOKS GREENLIT CAFE(港区南青山)」の運営
- 約3000坪の自社敷地を活用した各種イベントを開催
- 自社農場で野菜の有機栽培に挑戦
- サーキュラーエコノミーの実践 などなど
素敵な環境を創造し続け、世の中を笑顔で満たす活動をしている、大泉工場のKANです。
2012年。
もう13年も前になるのかと思うと、時間の流れの早さに驚かされる。
あの頃、僕は「オーガニック」という言葉に出会い、その概念に強く心を奪われた。
当時の大泉工場は、原宿を中心に巻き起こったポップコーンブームの真ん中にいた。
食材やマシン、そしてフレーバーのノウハウまでを提供しながら、毎日のように新しい味の開発や、出荷作業に追われていた。開発室には甘い香りが充満し、夜遅くまで続く試作の日々。いま振り返っても、あの熱狂は忘れがたい。
ポップコーンとの出会いは偶然だった。
ニューヨークのペンステーションで、ポップコーンを片手に街を歩く女性を見かけた瞬間、「これ、日本でも絶対に流行る」と直感した。根拠のない自信に突き動かされるように、僕はその世界に飛び込んだ。
運は努力の後ろ姿を追ってくる、という稲盛和夫先生の言葉があるけれど、あの頃の僕はまさにそうだったのかもしれない。
毎日ポップコーンのことを調べ、社内に開発スペースを無理やり作り、朝から晩までポップコーンと向き合い続けた。
夢中で動いたその先に、ブームはやってきた。事業は大きく伸び、全国各地から注文が舞い込む。僕自身も、走ることをやめられなかった。
ただ、どれだけ事業が拡大しても、心の片隅にはずっと“違和感”が残っていた。
なぜ僕はポップコーン事業をやっているのか。
心の底から語れる理由が見つからないまま、忙しさだけが積み重なっていくことへの不安。
それが、じわじわと僕を侵食し始めていた。
ある日、その違和感は決定的な形で姿をあらわした。
僕らが開発したポップコーンを食べられない子どもと出会ったのだ。
彼はアレルギーを持っており、僕らが「誰もがハッピーになれる」と信じてつくってきた甘くて濃厚なフレーバーのポップコーンを、口にできなかった。
その時の、なんとも言えない悲しそうな表情が今でも脳裏に貼りついている。
“僕の仕事は、この子を笑顔から遠ざけていないだろうか。”
その瞬間、僕は初めて、事業の「理由」を強く求めるようになった。
そんなタイミングで出会ったのが、オーガニックだった。
農薬や化学肥料、薬品をほとんど使わずに農産物を育てるという考え方。
それは、僕の中で欠け続けていた“なぜ”をすっと埋めてくれるものだった。
食が持つ本質に触れたような心地よさ。事業を通じて、地球も人も、笑顔になる。
そして、自分自身の中に「これを広めたい」という小さな炎が灯るのを感じた。
ただし、ビジネスとしては正解とは言い難かった。
当時の日本におけるオーガニック食品の市場規模は全体の0.2%。
ほぼ“ゼロ”に近い数字だ。
そこに全振りするということは、事業的リスクを抱え込むことと同義だった。
それでも僕は決めた。
既存のポップコーン事業や、先代から引き継いだ不動産事業で得た利益を投資するように、次々と事業をオーガニックへ切り替えた。
しかしスタッフからは反発もあった。「社長の趣味に付き合わされている」という空気が漂い、実際に多くの仲間が会社を離れていった。
正しかったのか。
ただの独りよがりだったのではないか。
夜中にそう自問したことは、一度や二度ではない。
僕の父は、心臓の病気で42歳という若さで亡くなった。
小さかった僕の目から見ても、彼の食生活は乱れていた。
もちろん、この出来事とオーガニックを直接結びつけるつもりはない。
けれど「食が人をつくる」という感覚が僕の中に刻み込まれたのは確かだ。
そしてその感覚は、オーガニックという概念と出会った瞬間、強く反応した。
海外に目を向けると、オーガニック市場は年々成長していた。
欧米ではすでに生活文化として根付いており、「地球にどう向き合うか」という問いの答えの一つとして実践されている。
これは単なる商品ではなく、生き方だ。
そのことに気づいた時、僕の迷いは消えた。
——日本でも必ずこの価値観が必要になる。
その想いだけで、僕は前に進み続けた。
そして2025年10月。
群馬県前橋市にある12haの有機小松菜農場「プレマファーム」が、大泉工場の子会社となった。
日本の農地面積430万haのうち、有機農地はわずか3万ha。
12haという規模は、数字だけ見れば小さな点に過ぎない。
それでも、この決断は僕らにとっては大きな一歩だった。
僕らがオーガニックに想いを託し、日本の農と食の未来に向き合うための“はじまりの場所”ができたような感覚だ。
僕はオーガニックをブームにしたいわけではない。
生き方そのものとして、社会実装させたいのだ。
もちろん僕らの事業すべてを、一気にオーガニックに変えることはできない。
そんな無理もしない。
ただ、確実に一歩ずつ進むことで、必ず市場は変わっていく。
大泉工場、プレマ、そして共に歩んでくれる仲間たちとともに、日本の食のあり方を前へ進めていきたい。
誰かの笑顔を遠ざけるのではなく、未来に笑顔あふれる希望を積み上げていくために。
僕たちはこれからも、オーガニックに想いをよせ続ける。
その想いが、社会の“当たり前”の一部になる日を信じて。