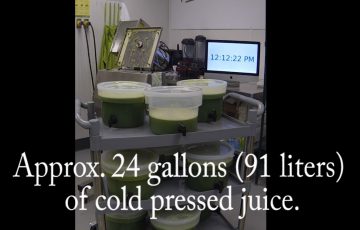今回コラムを担当します。大泉工場の内田です。
「朝の通勤途中、ふと、気付くと電線にすずめの姿がない。子供の頃にはどこにでもいてチュンチュン」と鳴き声が聞けた。」そんな気付きから昨年12月に「すずめを見なくなったね」を掲載させて頂きました。今回はその続編となります。
私が体現した幼少の頃(半世紀前)と今を比べてみます。
すずめだけではなかった

(カエル編)
田んぼに水が張られ、田植えの時期となると何処からともなく「ケロケロ」と聞こえてきたものです。雨が降った翌日の水溜まりで泳ぐ姿を見かけました。ときには、夜な夜な五月蠅いほどの鳴き声で睡眠を邪魔された記憶があります。
私は今年に入り、「ケロケロ」をまだ一度も耳にしていません。
(ホタル編)
稲の背丈も伸びた田んぼの夏の夜、稲の葉で羽を休めながら光っていたホタルたちが、静かに夜空を一斉に舞、幻想的な空間を作り出し光景に癒されていたことを思い出しました。
いまでは、ホタル観賞会でしか見ることが出来なくなりました。
気づけば、彼らの姿が日常からそっと消えていました。
もちろん、絶滅したわけではないと思います。少し郊外に足を延ばせば、まだ、カエルの合唱を聞くことも夜空を浮遊するホタルに出会うことも出来るでしょう。しかし、「当たり前の風景」だったはずのものが、今では特別な風景になってしまったことには間違えないと思います。
原因がいくつもあった

田んぼが宅地に変わり、用水路がコンクリートに覆われ、餌になる虫たちが減ってしまった。夜でも街頭や車のライトが眩しく、ホタルの光がかき消されてします。大量生産のための農薬や除草剤の使用、気候の変動、そして一番の原因は、自然に関心を持たなくなった私たち人間の暮らし方です。
どれも便利さと引き換えに差し出した自然。気付いたときには、戻すことが難しくなってしまった部分もあります。しかし、本当にこのままでよいのでしょうか。
わたしは子供の頃に、夜の田んぼに耳を澄ませ、ホタルの光を追いかけた、そんな体験は、大人になっても心の奥に残っています。(カエル編、ホタル編)いま思えば、言葉が正しいか分からないですが「自然とのつながり」だったのかもしれません。
まとめ
できることは、大きくなくても良いと思います。
ベランダに小さな水場を置いてみる、虫や鳥が戻ってくる庭をつくる。または、子供と一緒に自然に触れる時間を作るなど、身近なひとつひとつが、「隣人」と再び出会えるきっかけとなると思います。
静かに消えて行った彼らの声に、もう一度耳を澄ませてみようと思います。
あのチュンチュンという声が、いつかまた日常の当たり前に戻ってくることを願っています。
大泉工場CAMPUSは科学、芸術、自然を融合させた環境づくりに取り組んでいます。
「素敵な環境を創造する」ために循環型のコンポスト運用やコンブチャの製造の段階で排出される水蒸気や排水、廃棄物などを可能な限り減らし再利用し、地球環境にやさしい循環型農業を実践しています。
ぜひ一度訪れ、体感してください。