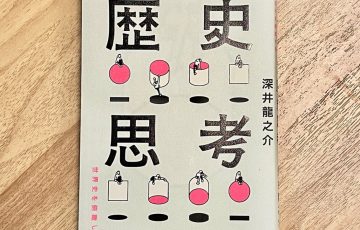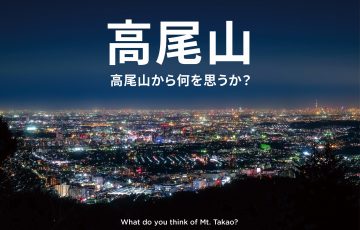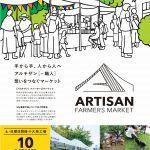- 機能性発酵飲料「_SHIP KOMBUCHA」の製造販売
- 100% Plant-Based/Naturalな素材にこだわったカフェ「1110 CAFE/BAKERY(川口市領家)、「BROOKS GREENLIT CAFE(港区南青山)」の運営
- 約3000坪の自社敷地を活用した各種イベントを開催
- 自社農場で野菜の有機栽培に挑戦
- サーキュラーエコノミーの実践 などなど
素敵な環境を創造し続け、世の中を笑顔で満たす活動をしている、大泉工場のKANです。
2012年、僕はアメリカから輸入したポップコーン豆を原料にした小さなビジネスを始めた。
ポップコーンが弾けるときの「ポンっ!」という音、香ばしい香り、はじける様子を見つめる子どもたちの目の輝き──その五感を揺さぶる体験は、僕にとって「食が人を笑顔にする」という実感そのものだった。
当時、児童養護施設などに出向いて、子どもたちと一緒にポップコーンを弾いて食べる活動をしていた。ところがある日、アレルギーを抱える子がその輪に入れず、悲しそうにしている姿を目にした。僕は深く考えさせられた。
「なぜ、アレルギーを抱える子どもがこんなにも増えているのだろう?」
「食べ物と、それを取り巻く環境が関係しているのではないか?」
その問いをたどる中で、僕は“オーガニック”という考え方に出会った。
日本のオーガニック市場の「現実」
2012年当時、日本のオーガニック食品市場はわずか0.2%前後のシェアしかなかった。
農林水産省の資料によれば、2009年で約1,300億円、2017年で約1,850億円という規模感だ。そして2024年時点の最新推計では、海外調査機関のレポートを円換算すると約2,500億円前後となる。
一方で、日本の食品産業全体の規模は90〜96兆円にのぼる。加工食品だけをとっても31兆円規模。
つまり、オーガニック食品は全体の0.2〜0.3%程度に過ぎない。
数字を並べると一目瞭然だ。僕らが「オーガニック」と呼んでいる領域は、まだ食品産業の“片隅”にしか存在していない。
世界市場を見れば違う姿がある。2024年のオーガニック食品市場は約2,700〜3,000億ドル(為替換算でおよそ40兆円規模)とされ、年々着実に伸びている。日本の2,000億円規模と比べると、桁が違う。
もちろん人口規模や食文化の違いもあるが、それでも「なぜ日本では広がらないのか」という問いは残る。
「最後の1ミリ」が欠けている
僕はその答えの一端が「デザイン」や「表現」にあるのではないかと考えている。
海外のスーパーマーケットに行くと、オーガニック認証を取得したグミやスナックが、子どもたちの目を惹くようなカラフルなパッケージで並んでいるのを目にする。値段も1ドル程度からある。そこには「ヘルシーだから食べる」だけではなく、「楽しそうだから手に取る」という動機がある。
一方、日本のオーガニック食品の棚を見てみるとどうだろう。
「素朴」「自然」「控えめ」といったトーンのパッケージが大半を占める。よく言えば誠実、悪く言えば堅物。確かに“体にいい”“地球にやさしい”ということは伝わる。だが、心が動かされるような楽しさや遊び心は、まだまだ少ない。
つまり、「オーガニックだからシンプルに」というルールを、商品そのものだけでなく、最後のプレゼンテーションにまで持ち込んでしまっている。僕はこれを“最後の1ミリ”と呼んでいる。この1ミリを軽視すると、本来持っている魅力が消費者に届かない。
デザインがつくる「自由なオーガニック」
人は一生のうちに約8万回の食事をすると言われる。
そのすべてを楽しくすることは難しいが、せめて手に取る瞬間くらいは「ワクワク」や「ときめき」があっていい。
デザインは、そのきっかけをつくる力を持っている。
- 開けた瞬間に笑顔になる仕掛け
- 裏面に隠されたちょっとしたメッセージ
- 二次利用できるような容器やパッケージ
- 思わず写真を撮りたくなる色彩や形
こうした“遊び”を仕込むことは、コストや規制との兼ね合いで簡単ではない。しかし、それをクリエイティブに乗り越えていくことこそ、これからのオーガニックの成長につながるのではないかと思う。
僕自身、海外の事例に刺激を受けながら、日本でももっと自由な表現を取り入れていきたいと考えている。その一つの答えが、_SHIP KOMBUCHA。世界で活躍するデザイナーのヒロ杉山さんに依頼をし、リブランディング後、売り上げは大きく伸長する結果となった。
オーガニックは「制約の象徴」ではなく、「可能性の実験場」になれるはずだ。
これからの課題と希望
もちろん、課題は多い。
- 生産コストが上がりやすい
- 認証や表示のルールが複雑
- 消費者の「オーガニック=地味で高い」という先入観
これらを一気に変えるのは難しい。でも、小さな工夫の積み重ねで、少しずつ“楽しいオーガニック”を当たり前にしていくことはできる。
例えば、地域の農産物とアーティストを組み合わせた限定パッケージ。あるいは、子どもが喜ぶキャラクターと一緒に展開するオーガニックスナック。
そうしたアイデアはすでに世界にはいくつも存在するし、日本でも始められる。
終わりに
僕が「オーガニックをもっと自由に」と言うとき、それは「真面目さを捨てよう」という意味ではない。
むしろ、真剣に取り組むからこそ、最後の表現には“遊び”を取り戻したいのだ。
体や地球のためになることはもちろん大事。だけど、人は「楽しい」「面白い」「ワクワクする」からこそ動く。
オーガニックがもっと自由で、もっと楽しいものになれば、きっとその選択は広がり、結果的に地球にも、私たち自身にも、より良い未来をもたらすはずだ。
僕はこれからも、この“最後の1ミリ”にこだわって、オーガニックの可能性を広げていきたいと思う。