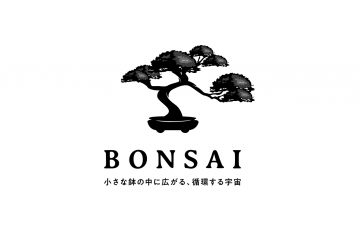こんにちは!デザインチームのJUNです。
大泉工場の掲げる『地球を笑顔で満たす』『素敵な環境を創造する』に共感して一緒に働いています。
先日、ラジオ番組を何気なく聞いていたところ、「かつてドン・キホーテ六本木店にジェットコースターを設置しようとしていた」という話題が紹介されていました。そういえばそんな話、あったなと懐かしく思い出すと同時に、今この話がなぜ自分の心に引っかかるのかを考えていました。
結論から言うと、それは“多様性”についてのヒントが隠れていたからです。

置かれる予定だったのは「ハーフ・パイプ」という種類のジェットコースターでスイスのインタミン社による
もの(下2枚)。実際に設置まではされたものの(上2枚) 稼働した際の振動がひどく、屋上では震度3ほどの
揺れが確認されたそうです。
ジェットコースターは「暴走」だったのか?
2000年代初頭、ドン・キホーテ六本木店が、ビルの外壁を囲むようにジェットコースターを設置しようとしていたという事実は、多くの人にとって「やりすぎ」「話題づくり」と映ったかもしれません。実際、住民や行政の反対もあり、最終的には実現には至りませんでした。
しかし、「非日常を日常に落とし込む」「エンタメを小売に融合させる」といった発想は、今の時代の体験型マーケティングの先駆けだったとも言えます。奇抜に見えても、「買い物を、もっと自由に、もっと楽しく」という価値観を、本気で空間に落とし込もうとしていた。そう考えると、そこには単なる“目立ちたがり”ではなく、現代にも通じる「商業空間のあり方」の挑戦があったように思います。
心斎橋の観覧車もまた「異物」だった
同様に、大阪・心斎橋のドン・キホーテの屋上に設置された観覧車も話題になりました。
建物にめり込むようにそびえ立つ円形の観覧車は、一見すると無駄で奇抜なアトラクションのように見えます。しかし、そこには明確な意図があります。「モノを売る空間に、人を呼ぶ」。つまり、商品だけでなく“体験”ごと提供しようという店舗戦略の一つです。
この思考回路は、通常のチェーンストア的発想——すなわち、効率性や標準化、フォーマットの再現性——とは一線を画しています。「ドンキはこうあるべき」「チェーンストアはこうあるべき」といった常識を裏切ることで、都市のなかに新しい風景をつくり出します。その風景のなかには、多様な人々がいて、日常と非日常の境界が曖昧になります。その“余白”にこそ、多様性は息づくのではないかと考えます。
街のど真ん中にそびえる観覧車は、当初多くの人から「浮いている」と言われました。けれど、観覧車はやがて“街のアイコン”となり、観光客や若者にとっては写真スポットとしても定着していきました。
つまり、「違和感がある」という第一印象を乗り越えた先に、“定着する個性”があるということです。

存在感あふれ、ランドマークの一つにもなっているドン・キホーテ 道頓堀店外観、と乗車イメージ
画一ではないことの価値
チェーンストアというと、一般的には「どこへ行っても同じ味、同じレイアウト、同じ価格」が魅力だとされてきました。しかし、ドン・キホーテのような一部の企業は、チェーンでありながら“地域ごとの違和感”を戦略的に仕込んでいます。
それは、“標準化”よりも“独自性”を重視する価値観の表れ。今、まちづくりや地域経済の文脈でも「多様性があること」「均質でないこと」が新たな価値とされており、それは「何ができるか」ではなく、「どう存在するか」を問うものです。
開かれたCAMPUSの思想と重なるもの
この視点から見ていくと、私たちが取り組む大泉工場のCAMPUSもまた、似たような発想の土壌に立っていることに気づかされます。循環型のライフスタイルや、地球に優しい選択肢を日常に組み込むための実験の場として、多様な事業やワークショップ、マーケット、農との接点が混在する空間を開いています。
ここでは、“完成された答え”を見せるのではなく、“今の過程”を共有しながら見せることがひとつの価値とされます。それは、決して効率的ではないかもしれませんが、「余白」や「意外性」が、体験としての魅力を生んでいます。場に「正解」をつくらないことが、結果的に多様性を育む余白になります。物販×体験、店舗×エンタメ、日常×イベント——あらゆる境界を溶かすことが、これからの商業空間や都市の価値のヒントになるのではないだろうか。

緑溢れるCAMPUS正面からの様子(上大)CAMPUSを活用したマーケットや、ライブラリーの様子(下)
まとめー「多様性を信じる」ことは、今の時代を生きる感性
多様性は「混ぜること」から生まれます。
ドン・キホーテの挑戦を、単なる“変わった店づくり”と片付けてしまうのはもったいないことです。むしろ、固定観念を壊すことを前提とした実験だと捉えることで、その姿勢はとても真摯で創造的な取り組みに見えてきます。
日本の商業空間は、ときに「整いすぎる」傾向があります。もちろん、美しさは大切です。しかし、それだけでは新しさや多様性は生まれにくいとも感じます。美しさと混沌、正しさとズレ、機能と遊び——そうした一見相反する要素が共存することで、人の想像力が刺激され、居場所の幅が広がっていくのではないでしょうか。
「なぜここに観覧車?」「屋上にジェットコースター!?」
そんな驚きの先にこそ、新しい発見や、思わぬ共感が待っているのかもしれません。多様性とは、異質なものが共存できる環境をどうデザインしていくか、という問いでもあります。そして、そのデザインには、ときに“非常識”の視点が不可欠です。
私たちもまた、大泉工場CAMPUSという場を通じて、“開かれた多様性”をどう形にしていけるのか。ドン・キホーテの都市伝説のようなアイデアに耳を傾けながら、私たち自身も、想像の限界を超えていく視点を持ち続けていきたいと感じています。
最後に
7月12日(土)、13日(日)にCAMPUSで(ARTISAN)FARMERS MARKET KAWAGUCHI が開催します。今回は酔鼓会の演奏やANIMANECTのドックランの催しも予定してます。ぜひCAMPUSの今を感じに遊びにきてください。